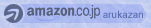
ある火山学者のひとりごと |
| 火山噴火・火山災害・地震災害・土砂災害のことなど、地球科学に関することなら何でも気軽に、書き込んでください。タグも使えます*。普段からいろいろ議論していて、緊急の場合には情報連絡板として利用してください。いったん書き込んだ後でも編集可能です。削除は本人と管理者が行うことができます。個人攻撃やデマや思い込み、不適切な発言はレスごと削除することがあります。掲示板上の発言は500まで表示されます。それを超える分については、アーカイバにすべて保存されており、過去ファイルのページで、いつでも参照が可能です。なお、あらしやロボット書き込み等防止のために、発言者のIPアドレスとブラウザ情報の取得を行っております。(アクセスカウンターは2005年8月1日より)。ロボットコメント阻止のために、画像認証を導入しました。 LINK TO[火山のページ][地球科学科][レーダー雨量][気象庁][ちばのアンテナ][Web魚拓] [ある火山学者のひとりごと研究]*)危険なタグは使用できません。ロボットコメントスパム対策のため、全角文字を含まない投稿はできません。管理上の理由で投稿や修正ができないことがあります。 |
| [浅間最新カメラ画像一覧][桜島監視カメラ][google scholar][GEOLIS] |
| Page47.75 / 50 Top | Bottom ← 936〜955件(保存数1000件) → | [HomePage] ▼ 投稿する ▼ 編集する ▼ 管理用 |
| 18365. 2012年12月28日 22時28分22秒 投稿:なべ |
| 暖房やら食料やらももちろんですが、当日は余震と瓦礫で家に入れません。とりあえず初日に夜露あるいは降雨を凌ぐのが第一、中越地震では車で寝る人が多数でした。避難所も必ずしも近くはないし。まず初日の安全確保、次に数日間の避難所と食料、そして長期の仮設住宅?しかし震災の度に困難を繰り返していますね。各家庭にテントがあると良いのでしょうが。 |
| 18364. 2012年12月28日 22時07分43秒 投稿:Hal.T [http://www.madlabo.com/mad/research/200603Leyte/Tdoc/index.htm#SEC5] |
| 東京の直下地震はもちろんだけど、東南海の地震は東北のように距離が遠いわけではなく、直下地震に当たる都市も多い。これが決定的に違う所。石巻や釜石は地震そのものではなく津波の災害でした。直下地震+津波なんてのが近代都市に襲いかかると何が起きるかわからないのが正直な所。 たとえば、東北では1mぐらいの沈下は当たりまえでしたが、静岡から高知まで1mでとどまるかどうか? 直下地震で破壊したインフラに加えて地盤沈下+津波。ちょっと想像もつかない。その他、都市伝説と言われていたいろんな災害の裏面に隠れていた犯罪を阻止する治安も無くなってしまいます(これはあまり言われない事ですが事実のようです)。 東南アジアの大災害では、最初に地方警察軍が出動します。装備はM16。彼らが最初に到着し周囲の治安を維持します。日本ではその体制はありません。犯罪者が跋扈することになり、自警団を考えておくべきかなとも思う。自警団と言えば関東大震災の嫌な側面がありますけれど、治安が維持されなくては救援者も被災者も救うすべがありません。中越地震では山古志村に入る全部の道に地元の消防団が立ち番しており、許可証を持っていても、ちゃんと確認するまで入れてくれませんでした。 助け合うためには、少々違法であっても、治安と指揮構造の整備が必須です。これらについて検討されている気配はまったくありません。指揮について言えば、警察と消防はそれなりに地元密着でいいんですけれど、なにしろ装備が絶無に近い。この50年つまはじきにされてきた自衛隊が口を出す雰囲気ではなく、自衛隊のせっかくの輸送力や通信と偵察技術もうまく運用しにくいと言う事です。つまり、ちょっと違法だっていいからせめて県単位で合意できる有能な全権指揮者がいなくては烏合の衆がする救援と言うことになってしまいます。 災害を予知するのもいいでしょうが、予知しても必ず起きることは起きます。私は予言ではなく、この10年間の災害を見ていて、我々日本人の危機対応が非常に民主的と言うか生ぬるく、無理なことは考えないと言うことが多いように感じます。無理を考える、そう、「あなたの携帯が使えない時」を想像してくださいと言うのはそう言う事なんです。東北の釜石では地震直後に携帯は全滅しました。津波で完全に壊れる前の話です。おそらく、静岡から高知まで、多くの都市では緊急対応のために役所から携帯通報を使おうとしているでしょう。いったい何を教訓にしているのか、それとも役所のやる気をアピールするだけなのか、不可解ですなあ・・・・ |
| 18362. 2012年12月28日 21時12分50秒 投稿:ちば |
| もしも、いま大地震が来て、インフラが破壊されて 長時間停電になったらどうするだろうと、考えてみた まず、暖房が止まる。パソコンも使えなくなる、サーバやルーターが止まるから ネットもだめ。エレベーターが止まり、電車が止まるだろう 道路はあっても信号がだめ、車は動くかもしれないが、タクシー待ちの長い列と大渋滞 自家用車のガソリンはあるだけ 停電になるとガソリンスタンドのポンプが動かないから、入れられない POSも動かないからお金のやりとりもできない。へたをすると現金がなくて ガソリンどころか何も買えず、なにも食えないかもしれない。 山の中でキャンプしているよう感じになるのか。 一斉に帰宅難民になるのだろう。仮に家にたどりついても食うものは何もない。暖房もないということかも ヨーロッパの冬のように、食糧備蓄1か月分かなあ。薪を積み上げて 3.11から何か学んだろうか |
| 18361. 2012年12月28日 14時21分07秒 投稿:Hal.T [http://www.wiss.org/WISS2012/InvitedLecture.html] |
| 死にそこないではあるが、最近は電子技術や情報分析を利用した防災観測から、災害そのものへの対応に世界が広がりつつあります。「災害はそこに人がいるから」と言われ、間違いではないのですが、「災害はインフラが壊れるから災害になる」とも言えると思うのが、この3/11の教訓ではないかしら。 阪神大震災以来、高度情報通信を利用したICT技術の利用と言う形で防災対策を進めている国ですが、その結果があのありさまと言えるでしょう。東北沖の深海津波計が設置されましたけれど、衛星経由で送られてくるならば、釜石沖にあった津波計と同じになるでしょう。東京やつくばの観測地でリアルタイムに見ていながら、被災地域に通報するすべが何もない。次もそんなことになりそうです。 URLは岩手県災害対策本部で動いていた秋冨医師の話がベースになっています。インフラがすべて壊れてしまった後の緊急医療の実情、治安と通信の崩壊が描かれています。東南海、東京の災害では想像もできないほどのインフラ破壊が連鎖的に被害を拡大する。3・11で見られたTVの情報すらないでしょう。 地域防災を担当している自治体の方は自分の携帯電話を見てください。その携帯電話が使えるのなら災害はたいしたことがありません。予想される災害では確実にその携帯電話は使えません。そうしたときに地域防災がどう動けるか、役に立つのかよく考えてみて欲しいと思います。もっか、私がお勧めする最強の近距離通信手段は遠足で先生が使う10Wぐらいの少し大きめの肩掛けハンドマイクです。これは誰にでも使え、自動車交通が無いのなら500m離れて会話できます。小集落の指揮をするならば防災無線よりも圧倒的な力を発揮するでしょう。 ふたたび書いておきます、大災害は確実にインフラを壊します。さて、どうします? |
| 18358. 2012年12月27日 12時10分24秒 投稿:ちば |
| Hal.Tさん> すみませんでした.齋藤先生へのリプライありがとうございます. ひるんで,うまくかけなかったのです. 掲示板は 議論には向いていないというかんじは わかります 壁に向かって 独り言を 話していると じつは 誰かが聞いてくれていて ときどき 反応がある そういうものだなあと おもって たいとるに ひとりごと と名前をつけました 書き込んでいる瞬間は みなひとりで キーボードに向かっているので でも,反応があると facebookよりも うれしいですね |
| 18357. 2012年12月27日 07時47分55秒 投稿:ちば [http://www.airpano.ru/360Degree-VirtualTour.php?3D=Kamchatka-Volcano-Plosky-Tolbachik] |
| ロシアのairpano ヘリコプターから撮影した高解像度全周映像 カムチャツカのトルバチク火山噴火中の映像 【注意】リンク先はデフォルトでBGMが流れます  |
| 18356. 2012年12月27日 07時33分39秒 投稿:ちば [http://www.airpano.ru/360Degree-VirtualTour.php?3D=Kamchatka-Volcano-Plosky-Tolbachik] |
| ロシアのairpano ヘリコプターから撮影した高解像度全周映像 カムチャツカのトルバチク火山噴火中の映像 【注意】リンク先はデフォルトでBGMが流れます  |
| 18354. 2012年12月25日 21時05分56秒 投稿:ちば [http://www.jishin.go.jp/main/chousa/12_yosokuchizu/index.htm] |
| 斎藤先生> 違和感というか,残念な感じがします. たしか、昨年公表しなかったのは、地震の規模が大きく、 予想だにしていなかったM9.0ということもあったのでしょうが 当時の発生確率の計算法では、2011.3.11の影響を、うまく反映できない。 巨大地震が発生したのに、直前と発生確率がほとんど変わらないのでは おかしいから、と読んだ覚えがあります。 今年の公表値は、関東地方など、いろいろ変っているところもあるので、 巨大地震の影響を、考慮できるような方法になったのかなあと 思っていました。リンク先を見るとまだ検討途中のようですが, だから公表しないわけにもいかないので,出すのだと・・・ 地震屋さんたちのやりかたもいいのですが 地質学の成果をもっと生かすべきだろうと 大まかに言えば,1000年に1回位の頻度で津波堆積物がみつかっていて 最後の貞観津波は1000年くらい前,ちょうど満期だった そういう観点での情報提供は何かできないのか |
| 18353. 2012年12月25日 17時53分11秒 投稿:齋藤 |
| 3.11で大外れした(兵庫県南部地震以降に遡っても、発生した場所は確率の低いとこばかり)にも関わらず、推本から全国地震動予測地図が公表されました。前回の予測で仙台は4%であったこと(低いのは安心情報でないと断りつつ数字をあげている)など、どう捉えたら良いのか、統計上の数値にしても0.1%までの数値に意味があるのか、一般に公表される図(数値)としては違和感を覚えるのは、私だけでしょうか。 |
| 18351. 2012年12月24日 15時35分15秒 投稿:ちば [http://www.jsce.or.jp/branch/kanto/01_04_gijyutu/school/koshuu_130201.html] |
| 講習会「富士山の噴火に備える」 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震(M9)を契機として、各地で地震が頻発しており、日本の地震・火山活動は新たなステージに突入したとの報道がなされています。なかでも、震災直後の3月15日に富士山直下で発生した地震は、富士山噴火が目前に迫った事象の現れとして緊張が一気に高まりました。その後、富士山は平穏を保っていますが、近い将来、噴火に至るだろうとマスコミ等で報道されています。富士山が噴火すると、関東地方には火山灰が数十cm(場所によっては数m超)、都内でも数cmから10cm程度のオーダーで積もり、交通網や通信網、下水等の都市インフラが麻痺し機能不全に陥るなど、これまで経験してこなかった災害に市民生活が大きく脅かされることが懸念されています。市民の安全を確保するためには、富士山噴火を見据えて様々な備えをしていく必要があります。 今回の講演会では、まず火山噴火予知連絡会長の藤井先生から、富士山の噴火はあるのか、あるとすればいつ頃なのか、我々にはどのような備えが必要なのか等についてご講演をいただきます。 また、お二人目の赤色立体地図発明者の千葉技師長からは、赤色立体地図の防災の活用法などについてご講演をいただきます。赤色立体地図は、地表の凹凸を直感的に素早く確実に認識することができる手法として最近テレビ番組等でも注目を集め、特に、災害の発生や防災・避難などを考える際に大きな効果があると期待されています。講演では、富士山の凸凹情報から過去の噴火事例等についても解説していただく予定です。 本講習会を、富士山噴火や防災の備えの一助にして頂けたらと考えています。多数の皆様の参加をお待ちしております。 記 1. 主 催 公益社団法人 土木学会関東支部 2. 期 日 2013年2月1日(金) 13:30〜17:10(13:00から受付開始) 3. 場 所 土木学会本部2階大講堂(JR中央線四ツ谷駅下車四谷口徒歩5分) 160-0004 新宿区四谷1丁目無番地(外濠公園内) 4. プログラム 13:30−13:35 開会挨拶 技術情報部会主査 13:35−15:15(100分) 富士山の噴火に備えて 火山噴火予知連絡会長 CeMI環境・防災研究所長 東京大学名誉教授 藤井敏嗣 15:15-15:25 休憩(10分) 15:25-17:05(100分) 赤色立体地図でみる地球の凹凸と防災への活用 アジア航測(株) 総合研究所技師長 千葉達朗 17:05-17:10 閉会の挨拶 5. 会 費 会員2,000円 非会員3,000円 学生会員1,000円 (消費税込み,会員は個人会員及び法人会員) 6. 定 員 120名(定員になり次第締め切ります) |
| 18349. 2012年12月23日 19時04分42秒 投稿:ちば [http://cgi4.nhk.or.jp/hensei/program/p.cgi?area=001&date=2012-12-28&ch=21&eid=12758] |
| 砂防工事が続き 一般観光客が立ち入れない立山カルデラを紹介する番組があるそうです NHK総合 2012年12月28日(金) 午後3:15〜午後4:00(45分) 年間100万の観光客が訪れる立山連峰。 実はそのすぐ隣に、大地の崩壊を防ぐため100年に渡って工事が続くかつての火山の崩壊地、 「立山カルデラ」が広がっている。一般の人はほとんど足を踏み入れない「秘境」。 古代遺跡を思わせる壮大なダム、市民の安全を守るため働く男たちの心意気… 立山カルデラ砂防博物館 TOPページ 立山カルデラの写真ギャラリー |
| 18348. 2012年12月18日 00時35分14秒 投稿:ちば |
| 今日は、午後から日本テレビの取材。 ニッポン創造という番組。 赤色立体地図は、なぜ赤いのかという質問が またありました。 赤が一番立体的にみえるとか、 微妙な彩度の違いがわかるとか説明した でも、目が疲れないとかもあるかな |
| 18341. 2012年12月14日 18時56分20秒 投稿:ちば [http://www.ch-japan.com/ja/] | |
| 今度の日曜日のチャンネルジャパンに出演します TBS「夢の扉+」の番組からいくつかを選んで 海外向けに放送するのだそうです
| |
| 18339. 2012年12月14日 11時46分04秒 投稿:ちば |
| 「その、実験台の引き出しには、ずいぶん前に失くして、ずっと探していた、 私の大切だった物がいっぱいはいっていた。 取り戻すことができて、とてもうれしかった。 しかし、いくつかのものはすっかりダメになって、茶色になってしまっており、 袋から出して流しに捨てた。」 という夢をみた。 |
| 18338. 2012年12月12日 19時50分52秒 投稿:ちば [http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/tsuruga_hasaitai/20121210.html] |
| 敦賀発電所敷地内破砕帯の調査に関する有識者評価会合 |
| 18336. 2012年12月07日 08時46分57秒 投稿:ちば [http://www.volkstat.ru/foto-ANO/index.php?event=showimg&msnum=13727] |
| カムチャツカ半島のトルバチク火山の溶岩流下の様子 |
| 18335. 2012年12月06日 22時16分00秒 投稿:ちば [http://www.gsj.jp/researches/gsj-symposium/sympo20/sympo20-program.html] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来年の1月22日に開催される 産総研シンポのプログラムです 転載します 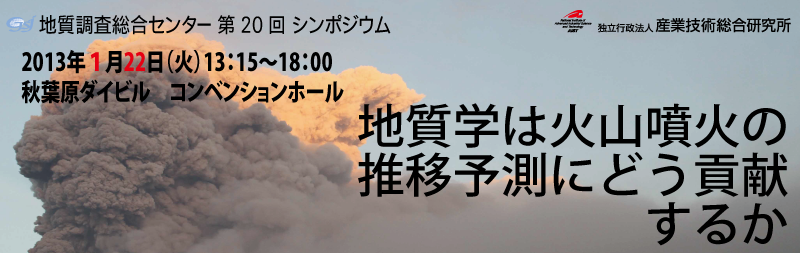
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18334. 2012年12月06日 22時10分01秒 投稿:ちば [http://www.gsj.jp/researches/gsj-symposium/sympo20/index.html] |
| 産総研では、多様な噴火現象を理解しその活動推移を予測するために、地質学的・物質科学的な調査・研究を行い、噴火履歴の把握とそれを引き起こしたマグマ活動機構の理解を進めている。本シンポジウムでは、火山噴火推移予測への地質学・物質科学の貢献について、産と官の立場からご講演頂くとともに、産総研で行われている最新の研究成果を紹介し、火山国日本において「安全で安心な社会を構築」するための研究のあり方について議論する。 開催概要 タイトル 地質調査総合センター第20回シンポジウム 地質学は火山噴火の推移予測にどう貢献するか 日時 2013年1月22日(火) 13:15〜18:00 会場 秋葉原ダイビルコンベンションホール→<アクセス> (東京都千代田区外神田1-18-13 秋葉原ダイビル2階) 主催 独立行政法人産業技術総合研究所地質調査総合センター 後援 一般社団法人全国地質調査業協会連合会 参加費 無料 |
| 18333. 2012年12月06日 12時38分45秒 投稿:ちば [http://www.geocities.jp/f_iwamatsu/retire/taisho.pdf] |
| 石黒曜さんが「死都日本」という小説の中で、霧島が破局噴火したら どうなるか、そして日本がどうなるかというシミュレーションを展開しています。 このような噴火が、近い将来桜島で起こる可能性についてのことだと思いますが、 もちろん、小さい確率でもいつかは起こるので、ゼロではないのですが、 現在の桜島の状況は、大正や昭和の噴火のような、 山腹からの溶岩流出というパターンを 念頭に置いて、注意をしている、という感じだとおもいます。 |
| 18332. 2012年12月05日 23時49分55秒 投稿:桜島 |
| 12月2日の朝日新聞に火山のことについて書いてありました。大規模な噴火が近年起きていないことはマグマの蓄積を示している「将来的に大噴火が起きる可能性がある」桜島のマグマはあと10年で大正噴火前の水準に達する見込みだ。とかいてありましたが、もし、桜島が大噴火すれば、東日本までに灰が降るんですか? |
| ← 936〜955件(保存数1000件) → |